「中ノ倉峠」本栖湖、千円札の逆さ富士展望台
僕はスノーシューで雪山を駆け巡るのが生きがいで、13年、イヤ15年かな、ずっと毎年冬になるとスノーシューに明け暮れていたのですが、7~8kg痩せてしまって脂肪が身体からすっかりなくなった事によって身体の保温力が落ちたからだと思うのですが、今までは耐える事ができていた-20℃の低温に全く耐えられなくなってしまい、毎年恒例のスノーシューの山域に行けなくなってしまいました。
僕はスノーシューが本当に大好きだったので、スノーシューができなくなってしまった事が本当にショックで、ちょっと立ち直れないかも知れないと思ったのですが、しかし山は他にもある、ココは開き直るしかないという事で冬の間は雪山よりは標高の低い山域に赴くようにしました。
今回は「千円札の逆さ富士展望台」でおなじみの本栖湖畔「中ノ倉峠」で先生(富士山)を撮影に行きました。※僕は山の事を先生と呼ぶのです、分かりにくくて申し訳ありません。

コチラは本栖湖畔にある駐車場です。トンネルの手前にあります。ココがスタート地点になります。※僕は日の出のグラデ―ションの空を撮影するのがライフワークですので日の出時刻の4~5時間前にヘッドライト、ハンドライトでスタートするスタイルになります。ですので紹介画像は暗闇の中での撮影が多いですが、この山域に赴く方の参考には十分なると思います。

ココが登山道入口、トイレ、駐車スペースのすぐ横から上り始められるようになっています。

しばらく上っていると3分岐に差し掛かります。いま本栖湖から上ってきたところです。まず「千円札の逆さ富士展望台」展望台に向かいます。その後、撮影開始までまだ時間がありますのでパノラマ台の方まで足を延ばし、そこから戻ってきて日の出のグラデーション撮影をおこなう、という大まかな行動計画になります。



クマ注意の看板があります。どの山域に赴くのであれ「鈴」は必須ですね。僕は市販のクマ用の鈴が音がうるさすぎて、その音を8時間聞き続けるのが耐えられないので自分が耐えられるレベルの小さい音の鈴を自作して使用するようにしています。

コチラが今回の撮影予定ポイント。駐車場からだいたい15分から20分ほどで上って来られる距離です。初めて来ましたが、狭いですね。コレは三脚をセットして撮影するのはキビシそうです。

階段状に下に降りられるようになっています。このいちばん下からなら木の枝などの遮へい物がない状態で先生(富士山)をバッチリ撮影できますが、僕は自撮りもおこなうのでちょっとこの撮影ポイントはキビシイかなぁ、と思いつつ、撮影時間までまだ時間がありますので一旦戻ります。

さぁ先ほどの3分岐から「パノラマ台」への上りセクションに突入します。コースは分かりやすく、まずルートを間違える事はないと思われますが、これからこの山域に赴く方の参考になれば、という事で、上っている最中に発見した道標をひと通り画像にて紹介させて頂きます。見落とした道標があったらご勘弁を。何しろ上っている時ってだいたい下を見てますからね。まず最初に遭遇した道標がコチラ。

続いてがコチラ。画面左から上ってきたんですよ。右に上ってるんですよ。

はい、雪が深くなってきました。ガスも出てきました。そのままガンガン上ります。

そろそろ上り続けるのがキビしくなってきた、というあたりでザックを下ろし軽アイゼンを出します。この軽アイゼンはかなり長い年月にわたって使用しているものでかなりボロボロ、ベルトは1回ブチ切れて、交換用ベルトに変えて継続使用しているという年季が入ったモノとなります。まだまだ使い続ける事になります。

軽アイゼンを装着し終わってさらに上っていくとさらに道標が。臨場感を損ねるので道標にかぶった雪は払わずにおきました。

はい、T字の分岐にぶつかってパノラマ台まであと少しのところまで来ました。T字の右がパノラマ台、左が三方分山方面となります。先ほどの3分岐からこのT字分岐まで、ひたすら上りセクションでだいたい1時間といったところでしょうか。僕はまぁまぁ足が速い方だと思いますので他の方々はもう少し到達時間がかかるかも知れません。行動時間に余裕をもって計画して下さいね。さぁ右に行きます。

T字分岐からパノラマ台までは距離的にはわずか、すぐ着きます。



はい、まだ暗い日の出前のパノラマ台に到着。今回の日の出グラデーション撮影ポイントはココではありませんので、暗くてもこのまま撮影して戻ります。僕はデジ一眼のISO値を上げて夜間撮影をおこなうようにしています。まぁまぁ明るく撮影でき、昼間の光の撮影では見られない変わった仕上がりになったりしますので、肉眼で暗闇にしか見えなくてもめげずに必ず撮影はおこなうのです。ヘッドライト、撮影用照明の効果で思わぬ雰囲気の撮影ができたりもするのです。

撮影時の気温-4℃。本当なら毎年この時期は-20℃の雪山にいるはずなのに、今はこの低山にいる。そう思うと悲しくなりますが今の僕は-4℃でも十分寒い。脂肪による保温力が落ちたのもあるでしょうが、悲しいかな、老化による保温力低下もあるでしょう。避けられない悲しい現実ですね。

さぁパノラマ台をあとにして「千円札の逆さ富士展望台」に戻ってきました。まだ日の出には早かったです、かといって立ち止まっていると一気に低体温になってしまいますので一旦上りセクションに戻って保温を維持しつつまた時間になったら戻ってきます。

この展望台は三脚をセットするスペースがほとんどありません。撮影にはかなりキビシイ場所という事が分かりましたが、来た以上は何かしら撮って帰らねばなりませんので根性でこのような撮影を。先生(富士山)のシルエットがわずかに見えます。階段のいちばん下から撮影すれば木の枝がかぶらず撮影できますが、自撮りスペースはありません。

で、空が白んできた頃に登攀セクションから戻ってくると何とある男性が階段の下に三脚をセットして撮影をしているのを発見。これでは僕は撮影できません。実は今日、僕はこの場所でムービー撮影もおこなう予定でいたのですが、思わぬ先客に計画が大いに狂わされてしまいました。残念ながらムービーは撮れなくなってしまいましたが何もせず帰る訳にはいきませんので根性で1枚だけこのように撮影しました。イヤー残念。

先客の男性は完全に居座っていて全く動く様子もなかったのであきらめて駐車場に下山します。登山道入口から先生(富士山)を眺められるようになっていましたので仕方なくそこで先生(富士山)のグラデーション撮影を1枚だけおこないました。雲ひとつない絶好のグラデーション撮影日和だったのに残念な1日となってしまいました。ま、最低限の撮影はできたのでヨシ、とするしかないですね。
…はい、今回のコースは行動時間もそれほど長くなくルートもむずかしい箇所はほとんどありませんでしたので道迷いはまずないものと思われますが、今後このコースに赴く方の参考になれば、という事で道標等の画像を複数UPさせて頂きました。パノラマ台まで行かず展望台だけでしたら1時間以内に行って帰ってこれる距離ですので、普段山に行かない方でも行きやすい場所なのではないでしょうか。
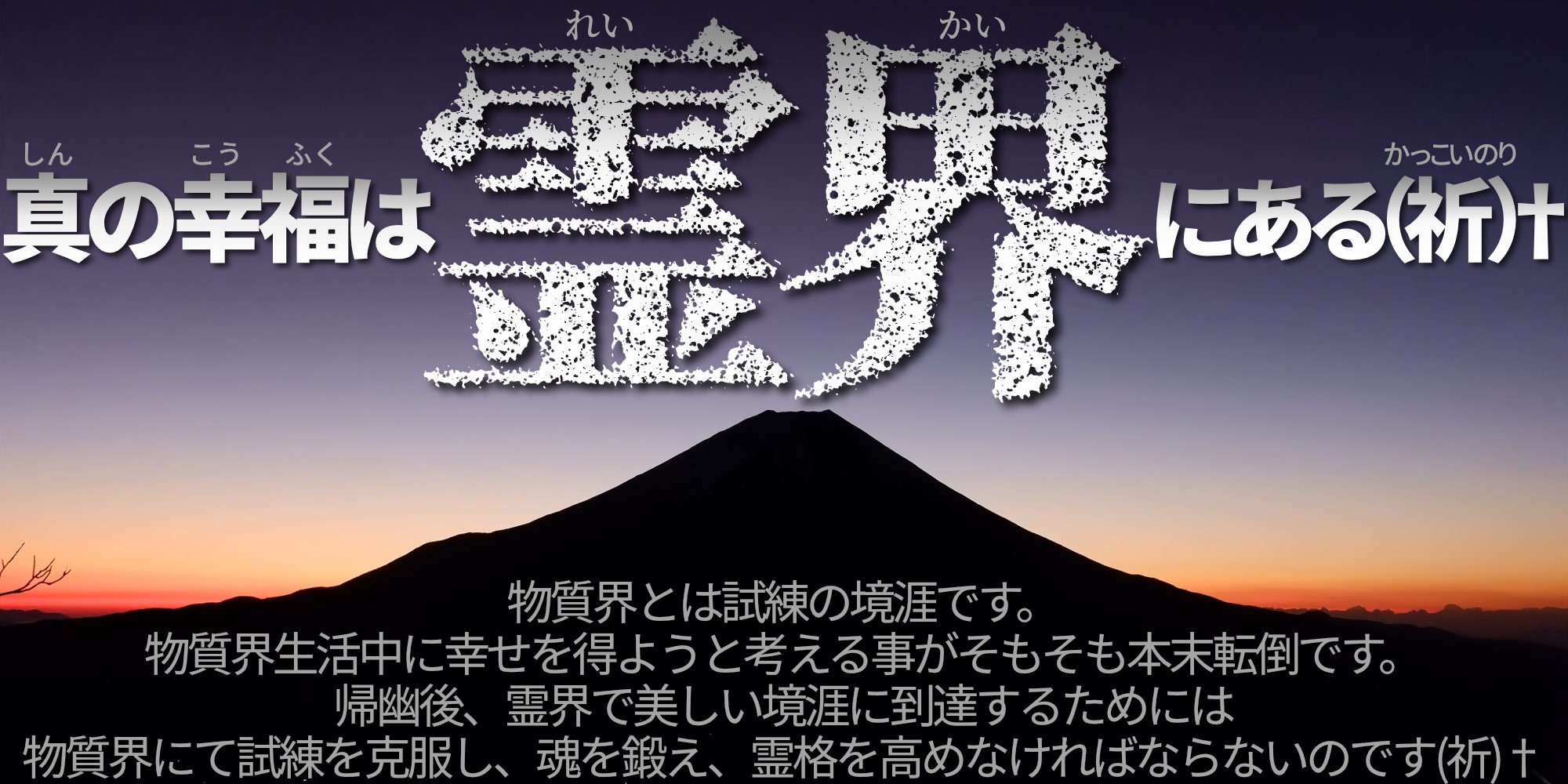














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません